いまどき、鎮守の森は絶滅危惧種かも知れません。
この備忘録は3回ほど連続で、映像に映し出され、写真にも撮られた玄界灘に浮かぶ沖ノ島の植生を端緒に、《森の保存と保全》について考えてきましたが、今回は《鎮守の森》に絞ってその歴史と変遷する植生について少し掘り下げてみることにします。
というのも、前回も少しだけ触れてはいるのですが、《鎮守の森》の林相は私が今までイメージしていたように《神聖な森とされ人為を排してきたためその土地本来の植生が今に残る》などというような簡単なものではないと、ぼんやりながらもわかってきたからです。
まず、下の写真をご覧になってください。この写真は近所の神社の、境内を囲む樹林が、一般に《潜在自然植生》のふるさとの森として畏敬されるような鎮守の森のそれとは違っていることを示すために、前回の備忘録《森の保存と森の保全(補足)》で使ったものです。この写真を改めて眺めてみると何だかヘンなことに気がつきます。よく見ると、樹林の左の方には伐採跡と思われる木の切り株がそのままにいくつか写っており、ここが鎮守の森だとすると、ますます乱雑で不似合いな印象を持ってしまいそうです。

問題の写真はgoogle mapから借用したものですが、これまで何度も初詣に訪れたことがある私の記憶を辿ってみると、ここには大きなスギの木が何本も並んでいたはずだと思い、自宅から5分と離れていない神社に実際に行ってみて現場を写したものが下の写真になります。

写真左は、google写真の左側に寄って撮ったもの。大木だけでなく細い幹の生育途中にある低木もついでに伐採されている様子が見て取れます。右は同じくその右側をアップで撮ったカットです。左と同様に下草刈りの施業をし、夏季(落葉)広葉樹だけを残しているこの作業は、里山の雑木林などの保全手法にも見られるものです。
当日、樹林の写真を撮りながら神社を一周すると、運よく林内を草刈り作業中の造園業と思しき方々に出会うことができたので、さっそく《神聖とされる神社の樹林をまるで雑木林のように簡単に伐採したり草刈りしたりしてもokなんですか?》とベタな質問をしてみると、帰ってきた答えは、何と《この神社の周りの樹林帯はすべて市有地であり、ここ横浜市の樹林保全の管理規則に則ってやってます。何か問題でも?》と、それはアイロニーたっぷりのものでした。神社の林ではなく、公有地だったという訳です。スギ群の伐採は、大木となり斜面に自立できなくなるという安全面からの措置なのかも知れません。
これで、鎮守の森にしては保全方法が少し乱暴ではないかという私の疑問もアッという間に解消し、と同時に私の単なる思い込みから抱いてしまった誤解が、神社にも迷惑をかけてしまったこととなり、恐縮の行ったり来たりという次第でした。
何だ、そういうことだったのか!?そこで、ここからは私の推測ですが、今から450年ほど前の室町時代に創建されたというこの神社の周りの鎮守の森は、それまでの安泰を打ち破られた1875(明治8)年のいわゆる「引き裂き上知」によって官有化*されたまま、戦後になってからは、その理由はわからないのですが、これを横浜市が引き継いで所有したのでしょうか。ともあれ、前回の「引き裂き上知」の記述部分を下に置いておきます。
■
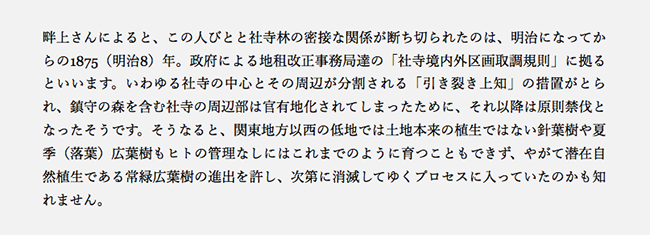
という訳で、私の今回の体験からでも推し量ることができるように、自前で鎮守の森を持っている神社は、今では珍しいのでしょう。宮脇昭さんが鎮守の森の激減ぶりを嘆いておられたのは、40年以上も前のことですから、今日ではさらに一歩進んで、絶滅危惧的な存在になってしまったのかも知れません。
宮脇昭さんの《鎮守の森》とその景観を再確認してみる。
さらに、上述の畔上さんの資料を拝見すると、私がこれまで持っていた鎮守の森のイメージが覆されるようなこともわかってきました。前回でも少しだけ触れましたが、「引き裂き上知」までの、つまり江戸時代の頃も含めた長い歴史のなかで、鎮守の森の景観は主にマツやスギそして夏季(落葉)広葉樹によって構成され、里山のようになっており、雑木林と同じように、燃料や肥料として人々の生活や農業にも利用されていたのではないかと思われます。
私は、これまで宮脇昭さんの著作をはじめとしてその周辺情報を知るにつけ、鎮守の森は昔から神聖な場として人の立ち入りが制限され、その植生に人為が及ばなかったために、従ってそこには、今も昔ながらのふるさとの木が残っているものだと、幸せな思いにふけっていました。実際に、家から数キロも離れていない場所にある師岡熊野神社の裏山(写真下)を訪れると、今もそこだけは多層群落を構成する常緑広葉樹の森が拡がり、神社の周りに残存する雑木林跡とはまったく異なる、自然で豊かな植生を見せてくれていいるのですから。

そこで、宮脇昭さんが歴史的な視点をふまえながら語られている彼の《鎮守の森》論を著作のなかから今一度引用してみましょう。
日本において特徴的なことは、我々の祖先は、自然の開発、古くには森の火入れによる焼畑、伐採による水田、畑、道路、集落、町、都市づくりに際して、いわゆる皆殺しをしなかったことである。新しい集落や町づくりに際して、一方においては自然の森を破壊して農耕地をつくり、薪炭林としての二次林もつくってきた。スギ、ヒノキ、マツなどの、建築材のための造林も行ってきた。しかし他方においては、必ず土地本来のふるさとの木によるふるさとの森を残してきている。それが、日本列島各地の神社やお寺や、古い屋敷、山の尾根、急斜面、渓谷沿いに今なお残されている土地本来の森であり、国際的にも、今そのまま言葉が使われている「鎮守の森』である。
■鎮守の森の周辺には、寺院や神社用の建材として、あるいは地域の象徴としてスギ、ヒノキ、マツが植えられ、老大木が今でも残されているところも多い。日光や箱根の杉並み木などは、その典型である。しかし、おおむねはその土地の、潜在自然植生、すなわち土地本来のふるさとの木によるふるさとの森が残されている。少なくとも高木層、亜高木層、低木層、下草層という土地本来の森の立体的な構成が残されている。(宮脇昭著『鎮守の森』新潮文庫 p61-62)
今日のテーマからすると、上の宮脇昭さんの文章中、特に興味深いのは次の箇所です。《鎮守の森の周辺には、寺院や神社用の建材として、あるいは地域の象徴としてスギ、ヒノキ、マツが植えられ、老大木が今でも残されているところも多い。》とありますが、鎮守の森の歴史を研究する畔上直樹さんによると、《スギ、ヒノキ、マツが植えられ》ていた場所は、宮脇昭さんのいう鎮守の森の周辺ではなく、事実はその内部であったことが『明治神宮以前・以後—近代神社をめぐる環境形成の構造転換』(畔上直樹他3名編 鹿島出版会 2015年)に詳しく書かれています。
《鎮守の森》のふるさとの森の景観が作られたのは、意外に新しい。
 畔上さんによると、大正—昭和期にかけて、とりわけ昭和の戦前・戦時期に、国は国家的神社の「林宛の本義」として以下のように定義し、推進しようとしていたのだそうです。《「元来神社境内の樹木はその郷土木を以って構成する」こと。「郷土木」とは「種が落ちて実生へその土地の自然林の一員として生育為しうる樹木」のこと。「神社の境内はその土地そのものが神ながらであって、古来の自然態をそのまま保続することに尊さが存する」》。つまり、今でいうところの土地本来の樹木=ふるさとの木である《潜在自然植生》を盛んに推奨しており、これを全国の神社にまで拡げようとしていたことがわかります。
畔上さんによると、大正—昭和期にかけて、とりわけ昭和の戦前・戦時期に、国は国家的神社の「林宛の本義」として以下のように定義し、推進しようとしていたのだそうです。《「元来神社境内の樹木はその郷土木を以って構成する」こと。「郷土木」とは「種が落ちて実生へその土地の自然林の一員として生育為しうる樹木」のこと。「神社の境内はその土地そのものが神ながらであって、古来の自然態をそのまま保続することに尊さが存する」》。つまり、今でいうところの土地本来の樹木=ふるさとの木である《潜在自然植生》を盛んに推奨しており、これを全国の神社にまで拡げようとしていたことがわかります。
これが事実であれば、今もわずかに残っている、昔から拡がっていたという《鎮守の森》の、土地本来の植生で構成されるふるさとの森の景観とは、意外にも昭和に入ってから、しかも人為的に国の政策として勧められカタチ作られたことになります。
しかし、何故これほどまでに国は、神社の樹林の植生のことに懸命になったのでしょうか。それは、当時の神社林がどんな林相を持っていたか、を見てみると理解できます。その一例をこの本の中から抜粋してみると、1942(昭和17)年滋賀県は県下の神職を集め「神社林苑講習会」を開いたのですが、そこで県の担当の次のような嘆きを発見することができます。《殆ど(の神社)が針葉樹を主木とし、常緑闊葉樹を主木となすものは、郷社以上の神社にあって十社に足らざる》状況であると。常緑闊葉樹とはもちろん常緑広葉樹を指しており、土地本来の自然の植生のものが殆どないと、その不満を報告しているのです。
このように当時の全国の《鎮守の森》の実態は、私たちのイメージを覆すものだったようです。前回備忘録では恥ずかしながらこの誤解のままに、常緑広葉樹林が保存されている神社の一例として名前を出してしまいましたが、当時は国家的神社(官幣神社)として上位にランクされていた大神(おおみわ)神社でも、実は同じような有様だったことがこの本から見て取れます。前回の繰り返しになりますが、この神社は三輪山自体を神体と位置付ける神体林神社の代表的な存在でした。ここの《鎮守の森》の景観も、時代の趨勢により大きな変更を余儀なくされていく、その経緯を畔上さんの記述から抜粋してみます。時代は1920年半ばまで遡ることになります。
大神神社側の県提出書類(昭和7年・1932年)によると、同社「神体林」はかつて「往時ヨリ林内ノ御掃除ヲ目的トシ、地元民ノ自由ニ枯枝落葉下草刈取等ノ入会慣行ヲ有シ林内ニ参入スルモノ多」という状況であり、1920年代半ばの状況としてほとんどがアカマツ林であった(残りはスギ、ヒノキ造林地)。このアカマツ林の形成が先の人為的な干渉圧力に関連するととも述べられており、「里山」的な景観だったと考えられる。上原敬二の批判する社会実態とは、このような状態に関連していると思われる。大神神社「神体林』の改造案において上原が主張したのは、もっとも神聖にする部分(拝殿直後の三つの鳥居付近)について、明治神宮の林縁整備同様、将来的に(その土地の気候的極相とされる)照葉樹林に移行させるための計画方針を樹立することであった。
大神神社側が実際に「神体林」三輪山の禁足地的管理の体制を段階的に整備しはじめるのは、先述のように上原の批判・提案からまもなくの1920年前後の時期である。大神神社は「神体林ノ精神ニ基キ且ツ保護ノ目的」で「三輪山掃除入山規制」を定め、「地元民即チ氏子」の下草採取の入山規制措置を部分的にとりはじめたのである。この入山規制が確立する画期は大正13年(1924)外部顧問(上原のような専門家も想定されるだろう)を交えた「神山保護調査会」の創設である。このもとで保護施業按が作成され、実施に移されていった。この管理体制は厳重なものであり、境内林を四つに区分、中核部を絶対神聖維持部分として禁足地とすることになった。禁足地部分について、「天然更新ヲ主トシ」て「漸次森厳ナル林相ニ導キ、且永遠ニ保続セシムル」ものとし、「撫育上必要ヲ生ジタルトキノ外、絶対ニ林木ヲ伐採セザル」ことが定められた。この原則は他周辺部分にもゾーンごとに様々な程度で求められ、全体として「自然」林への移行がめざされた。このように、上原の批判と同時期の1929年前後に、上原の批判と骨子を同じくする方針をもった「神体山の精神」による神体林管理体制構築につながる動向が大神神社側では生み出され、計画案が実行に移され、景観改造が進んでいったのである。原始古態的神社を厳重に守り続けているという、われわれの知る大神神社の少なくない部分が、意外にも新しく1929年前後の大神神社の動向に直接の起源をもっていることになる。(畔上直樹他3名編『明治神宮以前・以後—近代神社をめぐる環境形成の構造転換』 鹿島出版会 2015年 p83-85)
引用が、長くなってしまいましたが、これが三輪山自体を神体と位置付ける神体林神社の変遷の過程です(文中に出てくる上原敬二とは、あの明治神宮の森の植生を設計した本多静六のグループの一人)。上述の滋賀県の地域の人々の暮らしと共にあった神社の動向とも合わせて考えると、今でいう《潜在自然植生》への回帰がこの頃に、国家施業の一環として全国的に推し進められたことがわかります。
しかも、私たちが注目すべきは、大神神社の景観改造の経過報告にある文面についてですが、畔上さんは次のように書いています。《・・・昭和7年(1932)時点での実施経過報告は、きわめて印象的なことを語っている。施業計画により「常緑樹ノ刈取ヲ絶対禁止」したため、「近時著シク林相ニ変化」が起こり、「本山在来」のカシやシイ、ハイノキ、サカキといった照葉樹等「天然下種ニヨル幼樹ノ萌芽」が盛んになって「殆ント全山ニ渉リ混生」する状況となり、「寧ロ杉檜ノ苗木ヲ植栽スルノ不自然ナル作業ナルヲ痛感ス」ることになったというのである。問題が単なる景観改造なのではなく、その背後の新しい価値枠組の導入とその社会的受容も関わっていることが、ここにはよく示されていることになろう」》(同書p85)として、この次にその背後にある新しいものについて、論が展開されることになります。
が、《潜在自然植生》の学徒としてはここで留まって、まるで里山のような景観を見せていた山林に禁足地を設け、人為を規制した結果、わずか十年後には林相に変化が起こってきたことに注目しなければなりません。今ではその荒廃が社会問題化している里山の雑木林も人工林も、これと同じような植栽ルールを導入することで、十年ほど経てば、混交林の様相を見せはじめ、やがては土地本来のミドリが繁茂する自然へと回帰する可能性*にも着目すべきではないでしょうか。
■
しかも、当時は肥料や燃料の供給源として社会生活に不可欠な場所だったため、実は人々の大きな犠牲の上にこの全国の神社の景観改造が進められたのですが、今はその心配もないのですから。
神社林を《潜在自然植生》の森へ大転換したのは、明治神宮の森がキッカケ。
それにしても、長い間アカマツやスギなどの針葉樹や落葉樹が主木だったという里山のような景観を見せて近所の住民からも生活の糧とされていた神社林は、いつ・どこで180°転換するように、土地本来の自然の景観へと変更を余儀なくされることになったのでしょうか。
畔上さんによると、それは明治神宮の森の造園プランが決まり、神宮の植栽計画を主導した本多静六らが、今でいう《潜在自然植生》を採用したことが事の始まりだったそうです。
当初、本多は神社林にふさわしい樹種として、これまでの伊勢神宮や日光の東照宮に見られる針葉樹こそが神社の荘厳を発揮しうるといってスギやヒノキ、モミを考えていました。ところが、困ったことに明治神宮造園予定地の近くにあった渋谷の金王八幡や氷川神社の立派なスギ林が、都市化による煤煙など環境の悪化が原因でわずか数年のうちに急速に衰退してしまうという出来事が起こったことを知り、都市部に神社林を置くことに反対するようになります。
そして、大正3年(1914)明治神宮の鎮座地が正式に代々木に内定すると、本多は林学—造園学の立場から試行錯誤を重ねるなかで、当時は画期的とも言われた《明治神宮御境内林宛計画》を発表。この計画には畔上さんの文章を引用すると、次のように書かれていました。《神社の森の理想であるスギやヒノキ等の針葉樹林は、煙害に対する抵抗力が弱いため将来的に見て採用できず、抵抗力のある樹種への代替が必要となるが、それはカシやシイ、クスノキ等常緑広葉樹(照葉樹)を中心とすることとし、明治神宮が立地する土地本来の、原始の「自然」林態を「復旧」、植生が変化せずに世代交代をし続ける森を実現する。それにより、明治神宮林苑の都市立地と永久性を両立させる。このようにして、明治神宮が立地する土地の気象条件で「自然」のままに展開した場合の帰結=極相状態と考えられている照葉樹林形成にむけて、植生遷移を促進、短縮して実現させようという、本多静六いうところの「天然自然の偉大力たる森林」造形計画がまとめられた。》(同書p79)
このように、《潜在自然植生》の思想をそのまま実現しようとした明治神宮の森も、本多らの窮余の一策から生まれたという、実に危ういプロセスを経ていることがわかりますが、皮肉にもこれを契機に、全国の社寺林も同様の景観へと、まるで堰を切ったように大きな流れが生まれたという訳です。
以上、詳細は畔上さんの本『明治神宮以前・以後—近代神社をめぐる環境形成の構造転換』(畔上直樹他3名編 鹿島出版会 2015年)をご覧いただきたいのですが、期せずしておよそ百年前の歴史の上に突然生まれた「天然自然の偉大力たる森林」である鎮守の森も、あれから百年しか経っていない今では激減してしまい、もっぱらその短い歴史を閉じようとしているかのようです。
鎮守の森だけではなく、里山の雑木林もその歴史的な使命を失って久しく、今は荒廃だけがその後姿を覆っています。そして今となっては作り過ぎてしまったといっても過言ではないスギ・ヒノキの人工林もすでに成長し伐採期を迎えた今、自らの行き場を失ったままでいます。総じて日本の森は、右往左往の状態にあるようです。
こうして、私たちは森の保存とは何か。また森の保全というヒトの行為が今どういう結果を引き起こしているのか、再び最初のスタート台に戻って、かつて本多静六がそう試みたように、解決策をあれこれ考えてしまう時期に来ているのは、間違いありません。そして、私たちはこのピンチをチャンスに変転できるのでしょうか。
![]()


