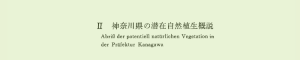沖ノ島の森は、ヒトを拒んだことで
1,000年以上の間、今日まで自然のままに《保存》されてきた。
先日この備忘録で取り上げた《世界遺産沖ノ島の潜在自然植生》は、沖ノ島が「神が宿る島」として昔から一般の人の立ち入りが禁じられてきたと聞いた時に、こういう1,000年以上もの間ほとんど人為が及ばなかった自然のままの森の植生とは一体どんなものだろうという素朴な興味がきっかけで、この島の写真展やこれと連動したtv番組、そして最近の学術調査レポートを見たり読んだりしたものを整理して書いたものです。

例えば、島のこんな写真を前にすると、はるか昔の縄文人が眺めた森の風景と同じようなものを見ているような気がします。昔の人は、なんだか得体の知れない、説明することもできないような現象や事象が今にも起こりそうな森へと入るには、かなりの勇気を必要としたはずです。自然現象のほとんどを解明してしまった現代人でさえ、写真のような森のなかに足を一歩踏み入れることは遠慮してしまうのかも知れません。実際、沖ノ島の森の道なき道を走破した調査団も、アブと山ヒルには閉口したとわざわざ報告書に書いているほどですから。
◎写真はbs朝日番組『沖ノ島~藤原新也が見た祈りの原点~』のキャプチャー画像、以下同様。



こんな調子の、私たちが日頃から見慣れている里山の雑木林とか整然と天に勢いよく伸びるような遠目にも美しい人工林とは、あまりにもかけ離れた顔を見せる沖ノ島の森の林相に、どことなくホンモノの自然らしさや普遍性を感じるのは私だけでしょうか。この小島は神が宿る島と言われてきましたが、これら写真に撮られた森には、神だけではなく、何やら怪しい魔物らしい超自然的なもの*も出てくるような雰囲気さえあります。
*民俗学者でもあり妖怪研究者!でもある小松和彦さんは、この「超自然的なもの」は二つに分類されるとして、一つは人々の富や幸いをもたらすものとしての「神」であり、もう一つがここに書いた「魔物」とか「妖怪」と呼ぶものであるとしています。
この(雑木林や人工林に比べて)自然でホンモノらしい樹林は、ヒトの援助はもちろん、ヒトが立ち入ることさえ拒否してきたこともあり、したがって、この千数百年という間私たちはこの森の《保存》に一円も払う必要はありませんでした。自然にしても建物などの人工物でも《保存》に多くのコストが発生することは世の中の常識ですが、こと自然の森の《保存》には、ヒトを排除する限りはコスト=0という逆説的な一つの事象をここに見つけることができます。
ところが、この沖ノ島に拡がるような土地本来の自然の森は、国内では古代よりヒトの手が入ることで破壊が続き、今となってはそのほとんどが消滅しており、常緑広葉樹林帯ではわずかに鎮守の森と呼ばれる社寺林や屋敷林として残されているだけで、宮脇昭さんによるとその割合は森の面積の0.06%に過ぎないとしています。落葉広葉樹林帯に目を移しても大きな面積を誇る自然林は、せいぜい東北地方の白神山地、日本海側の山地、下北半島にみるほどのようです。
そこで日本の森の全体を見てみると、そのほとんどを占めるのは人工林や雑木林です。ところが、森の主人公とも言えるこの二つの森は、どちらも困難な問題を抱えていることは、この備忘録で何度も指摘した通りです。主に住宅用建材として1950年代から国策のように植林され、その面積が1,000haにまで拡がってしまった人工林のスギやヒノキが今では伐採する時期は過ぎているのですが、安価な輸入材との競争に勝つことができず、伐採することも運び出すこともできないという深刻な状況が続いています。日本の林業はgnp比では0.1
また、化学肥料や化石燃料がなかった時代に、それらに替わるものとして人々の生活の必要から利用されてきたクヌギ—コナラなど落葉広葉樹からなる雑木林も、その役割が終わって久しく経っています。特に農業と密接な関わりを持っていた雑木林ですが、近くの農地は都市近郊だと住宅地に、地方では後継者不足などで農業を離れる人々が年々増加したことで、里山の雑木林はまるで歴史に捨て置かれ、荒れるに任せたような状態になっています。
なぜ、人工林も雑木林もこんなに困難な問題を抱えるようになったのか。それは、定期的にヒトの管理を必要とするところに原因があります。ヒトがコストとマンパワーを費やしながら持続的に保全することではじめて、この二つの林は維持することができていたからです。にもかかわらず、人工林はせっかく費用を投下しても、事業として経済的に成り立って行かないし、雑木林の場合は、管理する人々がいなくなった訳ですから、共に問題は深刻です。特に人工林の場合は、これ以上管理放棄を放置するわけにもいかず、行政が仕方なく税金を使うことで、山の持ち主に替わって間伐などの管理を代行しているという訳です。
では、このまま放置するとどうなるのか?仮に雑木林・人工林をヒトの影響をストップしてこのまま放置すると、200〜300年後には最終的にその土地本来の森に戻ることになります。が、同時にヒトへの影響も考慮すると、問題は簡単ではありません。
森の《保存》と《保全》、その違いを改めて考えてみる。
こんなことを考えていると、一年ほど前に備忘録にも載せたことがある植物生態学の研究者の講座のことを思い出してしまいます。講座では、自然を守ろうとする態度には《保存》と《保全》があり、残念ながら、この両者はまったく違うものだということを学ぶことができました。その部分を再録させていただきます。

このような観点からすると、里山の雑木林や人工林はどこから見ても「人間に被害が及ばないようにするために(あるいは、人間が利益を生むために)自然環境を保護」するという人間本位の《保全》であり、これとは対照的に沖ノ島の森と自然は人為を拒み続けたことで、結果的に《保存》されてきたと言えます。
ところが、(ここからが重要になりますが)沖ノ島の森に見られるようなその土地本来の植生から構成される森は、そのほとんどがヒトの生活や利益のために破壊されたために、今ではとっくに消滅してしまい、代わりに日本全国に里山の雑木林や人工林が生まれてしまいました。しかし今や立ち行かなくなった雑木林や人工林の《保全》のために、国や自治体は毎年莫大なコストを要しているというのが現状です。
おそらくですが、この先日本がこのまま高齢化・少子化社会に移行し、人口減少→税収減となることを考えると、近い将来には雑木林や人工林の《保全》にこのまま税金から費用をまかない続けることは困難になる可能性があります。そして、雑木林や人工林の《保全》をストップしてしまうと、これまで維持されてきた森の水源かん養機能など、森がヒトに対して持っていた多面的な機能が徐々に失われてしまい、環境の劣化が進行することにもなってしまいそうです。
《保全》する森から、《保存》する土地本来の森へ。
そこで将来に備え、日本の森の多くを占めている雑木林・人工林からその土地本来の自然の森林に少しづつ置き替える試みを始めてみるのはどうでしょうか。つまり《保全》する森から《保存》する森への転換です。
《保存》する森=その土地本来の森は、沖ノ島の森や明治神宮の森そして全国に残る鎮守の森がそうであるように、森を維持するコストやマンパワーなどヒトの《保全》はまったく不要。ただただ森のなかにヒトの手が入らないようにと《保存》を心がけるだけでいいのです。つまり土地本来の森の《保存》とは、この場合は何もしないことと同意義になります。
そうやって土地本来の森(標高800m以下の関東以西では常緑広葉樹の森)を全国で復元・再生することで、雑木林:人工林:土地本来の森=1:1:1あたりに揃えることができると、今の森の《保全》に関わるコストも2/3**程度に抑えることも可能です。
**雑木林や人工林に替わり、昔から繁茂していた土地本来の森を再生する作業には、植栽時の初期コストそして植樹から3〜4年間は必要となる下草刈りなどのランニングコストがかかることはもちろんですが、それが存在する限りは維持・管理コストが永久に加算される雑木林や人工林と違い、植栽から4〜5年以降は場所によっては必要となる獣害対策に関わるコスト以外は基本的に0と考えられます。これはすでに触れたように、ヒトが立ち入ることを禁じた沖ノ島の森や今も私たちの近くでわずかに残存する鎮守の森で立証されていることでもあります。(明治神宮の森の場合は、参道に舞い落ちる落葉を掃き清めて林内に戻すこと等を反復しているため、参道周辺の維持コストがありますが、これは多くのヒトが日常的に森へ侵入するために発生するものだと考えられます。)
しかも嬉しいことに、土地本来の常緑広葉樹林の場合、苗木から作り始める植栽技術もすでに《宮脇方式》として確立しており、その土地本来の低木—亜高木—高木からなる多層群落を構成する樹種のポット苗木×12〜15種類を宮脇昭さんが薦める混植・密植方式で植えることが一般的に行われています。この方式だと植栽後4〜5年たつと、年に数回の雑草取りなどの作業も不要となり、それ以降は自然任せの、文字通り自然が育ててくれるという訳です。そして10年前後が経つと林相は下の写真のように鬱蒼となり、林床には重なり合った落ち葉が徐々に分解されるプロセスにあるような、多様で豊かな生態系を育む常緑広葉樹林特有の、森の基本形を私たちに見せてくれるようになります。100年もすると、おそらく明治神宮の森のような、それ自体が永遠に栄えるような立派な森となるに違いありません。

この写真は今から9年前にnpo法人国際ふるさとの森づくり協会が高木・亜高木・低木の常緑広葉樹×15種類ほどの苗木を《混植&密植》という宮脇昭さんが推奨する手法により植樹したもの。この手法だと、植樹から3年間は雑草を駆除するなどの人手が必要になりますが、その後は一切ヒトの手が入ることはありません。そして植樹から10年近く経過すると、この写真のようにスダジイやタブノキを主木とする高木—亜高木—低木—草本類からなる多層的で豊かな森の基本的なカタチを自ら表すようになります。(写真は神奈川県湘南国際村)
下の写真は、植樹から9年を迎えるこの常緑広葉樹林のなかに分け入り、樹林の内部を撮ったものです。ストロボ光のために実際よりも明るく写っていますが、林床には主に落葉が地面を覆っているだけで、雑草はほとんど見つけることができません。ヒトの手による下草刈りなどの維持管理をストップしすでに5年以上の時が立っており、自然の環境のままに任せて育てた結果、樹林のなかはご覧の通りの状態です。

このように、林床に生える雑草が見当たらない理由は、第一に植樹された十数種類の多層群落を構成する樹木がすべて土地本来の木=潜在自然植生(上の写真の場合は常緑広葉樹)であることです。第二に、宮脇方式といわれる《混植&密植》の植樹法にあります。このあたりを宮脇昭さんご本人に少し詳しく語ってもらいましょう。
 《‥‥3〜5年経つと幼苗は2〜3メートルの高さに育ち、樹冠が林床を覆って、日光が林床まであまり届かなくなってきます。陽生***の雑草は生育困難になり、ほとんど雑草の生える余地はなくなります。したがって、植樹後4〜5年目からは、人間による管理は基本的に不要になってくるのです。この後は、自然淘汰によって、時間とともに、多様性に富んだ土地本来の多様群落が構成され、自然に近い森林生態系が形成されていきます。》(宮脇昭著『木を植えよ!』新潮新書 2006年 p173-174)
《‥‥3〜5年経つと幼苗は2〜3メートルの高さに育ち、樹冠が林床を覆って、日光が林床まであまり届かなくなってきます。陽生***の雑草は生育困難になり、ほとんど雑草の生える余地はなくなります。したがって、植樹後4〜5年目からは、人間による管理は基本的に不要になってくるのです。この後は、自然淘汰によって、時間とともに、多様性に富んだ土地本来の多様群落が構成され、自然に近い森林生態系が形成されていきます。》(宮脇昭著『木を植えよ!』新潮新書 2006年 p173-174)
***「陽生の雑草」に関連して付け加えると、宮脇昭さんは彼の著書『森の力—植物生態学者の理論と実践』のなかで、《森のなかは‥‥タブノキなどの高木が太陽の光を遮っていて、薄暗いなかでもモチノキ、ヤブツバキ、シロダモなどの亜高木と呼ばれる木々が育ち、ヒサカキ、マサキ、アオキ、ヤツデなど、海岸近くではトベラ、シャリンバイ、ハマヒサカキの低木、足元にはヤブコウジ、テイカカズラ、ベニシダ、イタチシダ、ヤブラン、ジャノヒゲなどの草本植物も‥‥。高木林内の亜高木、低木は陰樹といわれ、高木の樹冠から漏れる散光で生育できる日陰にも耐えられる植物です。》と「陽生の雑草」とは対照的な「陰樹」の特性についても言及されています。
関東地方以西の低地では、このような手法で作られたその土地本来の植生である《潜在自然植生》=常緑広葉樹林は、植樹から4〜5年経つとその後の成長にはヒトの手も管理コストも不要となり、ヒトの手ではなく土地の自然環境が育ててくれるという人工林や雑木林など他の植生にはない優れた特長を備えていることがすでに多くの場所で実証されています。こうして《保存》する森は命を守る自立した循環システムとして、陸や海をめぐる地球の生態系を支えてくれることになります。
これが、文字通り未来の人たちへの贈り物として、最適な森のカタチだと確信しています。
![]()