今年の文化功労者に民俗学者の(というよりも妖怪研究者として名高い)小松和彦さんが選ばれたと、先日の新聞に載っていました。私の場合は、宮脇昭さんの《潜在自然植生》に関わる著作を読んでいるうちに民俗学、特に縄文期にまで遡る照葉樹林文化や鎮守の森と神社の歴史などにも興味の手が伸びてしまい、そのなかの一端が神や仏の世界、つまるところが自然と人間の土着の関係を捉えようとする民俗宗教に行き着いてしまったという訳です。
そのなかでも、最も興味深いものの一つが、昔から人の手では制御しえなかった超自然の象徴である神とその対極に位置付けられた妖怪の物語であり、とりわけ妖怪学の第一人者である小松和彦さんの言説に他なりません。ここで、小松さんの「妖怪」定義を『日本民俗文化体系4 神と仏 第6章 魔と妖怪』から引用しながら、少し聞いてみましょう。
■そこで、民俗社会に登場する「超自然的存在*」を、「妖怪」とか「魔」として記述する場合のさしあたっての定義を述べておこう。■「妖怪」とは、世界に生起するあらゆる現象・事物を理解し、秩序づけようと望んでいる民俗社会の人々が持つ説明体系の前に、その体系では十分に説明し得ない現象や事象が出現したとき、そのような理解しがたいもの、秩序づけできないものを、とりあえず指示するために用いられる語である。古代人はこれを「もの」と呼び、その出現の徴候を「もののけ」と呼んでいた。つまり「妖怪」とは、正体が不明のものであり、正体不明であるがゆえに遭遇者に不思議の念、不安の念をいだかせ、恐怖心を生じさせ、その結果「超自然」の働きをそこに認めさせることになる現象・事象を広く意味しているのである。(かつては、「もの」「妖怪」と並んで「百鬼夜行」「妖物」「魑魅魍魎」などといった言葉も用いられていた)言い換えれば、民俗社会がもつ二つの説明体系、つまり「超自然」を介入させない説明体系と「超自然」を介入させた説明体系、の間を揺れ動いている正体不明のものが、人々の認識家庭の第一段階の「妖怪」なのである。そして、正体不明であるがゆえに、人々に不安や恐怖心を起こさせるので、この段階の「妖怪」も、人々にとって好ましいものではないといえるであろう。しかし、この段階では、まだ人に対して危害を加える邪悪なもの、といった明確な判断を下すまでには至っていない。
■ところで、こうした二つの異なった説明体系の裂け目に立ち現れてきた正体不明の「妖怪」を、民俗的思考はどう処理し秩序づけようとするのであろうか。それは結局、民俗社会が所有する思考体系つまり民俗的思考が、「超自然」の介入に頼らずに「妖怪」の正体を究めることができるか、それとも、それができないために「超自然」の領域に組み入れて説明しようとするか、の二つのうちのいずれかを選ぶことによって決まる。(『日本民俗文化体系4 神と仏 第6章 魔と妖怪』小松和彦著 p345-346 小学館 1983年)
■
*小松さんは、この「超自然的存在」は二つに分類されるとして、一つは人々の富や幸いをもたらすものとしての「神」であり、もう一つがここで取り上げている「妖怪」とか「魔」と呼ぶものであるとしています。
このように妖怪の定義づけをするのですが、結局それは《正体不明のものの正体を科学的・合理的に究めつくすことができなかったとき、民俗学的思考は、それを超越的・非科学的説明体系のなかに組み入れて秩序づけようとすることになる》と、何事にも納得しないと気がすまないというヒトの心性にたどり着くことになります。
ところが、特に近代以降は時代が進むにつれ、科学優位の傾向とともに超越的なものも次第に少なくなったのか、都市化の波が自然を覆い隠そうとしていることも加わって、最近は妖怪の話しなどはほどんど聞くこともなく、せいぜい私たちは水木しげるさんの妖怪漫画で超越的・超自然的な渇きをしのぐしかありませんでした。
とはいえ、現在でも少なからぬ人たちが、多かれ少なかれ、たとえそれが後から思うと、気の迷いだったり考え違いだったとしても、一度ぐらいは超越的・超自然的な事物・場面に出会ったという経験があるのではないでしょうか。私はそれに、見るからにかつては薪炭林であった二次林と思われる森のなかで一度遭遇したことがあります。もっとも、私の場合はその現象が少し不思議に思われた程度で、不安や恐怖心とは無縁のものだったこともあり、妖怪!と声に出してしまうには、実にビミョウなカンジなのですが。
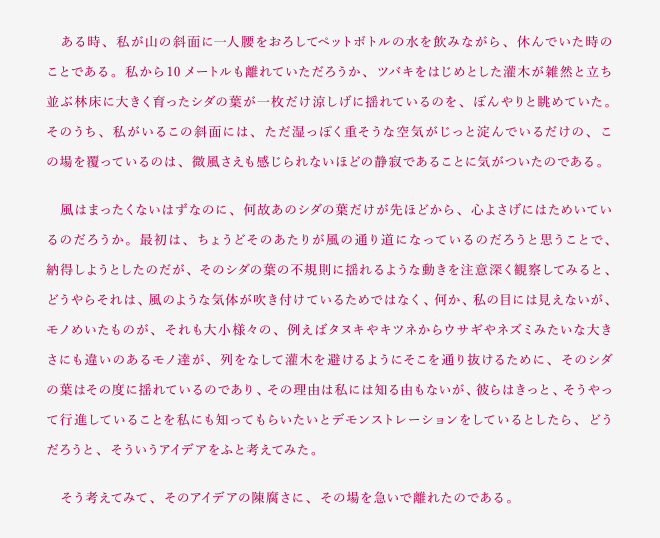
改めて、この文面を読み返してみると、もう少しで姿を見せようとしている子犬ほどの小さな《もの》たちは、妖怪よりは精霊と呼ぶにふさわしい趣きを持っているようですが、問題は風になびくように揺れていたその一葉の大きな葉っぱは、本当にシダだったのでしょうか。もしかすると、ランの仲間で大きく厚い葉をつける草本だったような気もしてきます。ここで、念のために森に育つ草本類のことを宮脇昭さんの本から抜き出してみましょう。例えば、雑木林の場合。
…数百年続いてきた里山の雑木林の伐採や下草刈り、落ち葉掻きも行われなくなった。そこで、遷移の途中相の状態で伐採、下草刈りなどの人為活動によって足止めされていた二次林の、雑木林のまわりに自生していた、ツル植物やネザサなどが林内に侵入してくる。関東ではアズマネザサ、関西ではネザサやメダケ、ススキ、チガヤ、カリヤスモドキなどの草原性のイネ科植物や、キンラン、ギンラン、シュンランなどランの類の草本植物、林縁群落すなわちマント群落の構成種であるクズ、カナムグラ、ノブドウ、ヘクソカズラ、エビヅル、あるいは伐採の後に出てくる棘のあるキイチゴ、野イチゴ、サルトリイバラなどが林内に入って、雑木林は荒れてやぶ状になる。いわゆるジャングル状になってしまってる。
■よく森とジャングルを混同されることがある。ジャングルといわれる人が入り込めないような低木やツル植物の混生・密植植生は、土地本来の森であればその周辺に、せいぜい幅が50cmから1mぐらいまでである。すなわち、本来の森は、高木、亜高木、低木、下草と見事な階層で垂直的、立体的な森社会が形成されている。
■通常、土地本来の樹林が草原、水際、道路などの開放景観に接しているところでは、ツル性植物や半分日陰、半分日向で育つ林縁性のウツギ、ヤマザンショウ、ニワトコ、ヌルデ、ムラサキシキブ、ツルウメモドキ、ヘクソカズラなどがまわりを囲んでいる。これはいわば自然の森の番兵として森林内へ急に光や風が入って林床が乾いたりして森が破壊されないように森の保護組織として機能している。
(宮脇昭著『鎮守の森』新潮文庫 p56-58)







 (この稿未完)
(この稿未完)
![]()


 …数百年続いてきた里山の雑木林の伐採や下草刈り、落ち葉掻きも行われなくなった。そこで、遷移の途中相の状態で伐採、下草刈りなどの人為活動によって足止めされていた二次林の、雑木林のまわりに自生していた、ツル植物やネザサなどが林内に侵入してくる。関東ではアズマネザサ、関西ではネザサやメダケ、ススキ、チガヤ、カリヤスモドキなどの草原性のイネ科植物や、キンラン、ギンラン、シュンランなどランの類の草本植物、林縁群落すなわちマント群落の構成種であるクズ、カナムグラ、ノブドウ、ヘクソカズラ、エビヅル、あるいは伐採の後に出てくる棘のあるキイチゴ、野イチゴ、サルトリイバラなどが林内に入って、雑木林は荒れてやぶ状になる。いわゆるジャングル状になってしまってる。
…数百年続いてきた里山の雑木林の伐採や下草刈り、落ち葉掻きも行われなくなった。そこで、遷移の途中相の状態で伐採、下草刈りなどの人為活動によって足止めされていた二次林の、雑木林のまわりに自生していた、ツル植物やネザサなどが林内に侵入してくる。関東ではアズマネザサ、関西ではネザサやメダケ、ススキ、チガヤ、カリヤスモドキなどの草原性のイネ科植物や、キンラン、ギンラン、シュンランなどランの類の草本植物、林縁群落すなわちマント群落の構成種であるクズ、カナムグラ、ノブドウ、ヘクソカズラ、エビヅル、あるいは伐採の後に出てくる棘のあるキイチゴ、野イチゴ、サルトリイバラなどが林内に入って、雑木林は荒れてやぶ状になる。いわゆるジャングル状になってしまってる。
